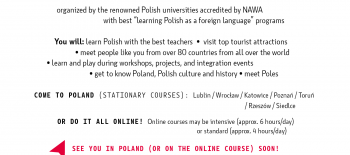2021年6月11日に、「ショパンとの午餐」を開催しました。
会場は、代官山にあるフレンチレストラン パッション(PACHON)。 フランスにあるレストラン「リッチェル」に残されたメニューとレシピ。それは、かつてフリデリク・ショパンがパリで生活していた時代のものでした。
そのメニューを再現し、ショパンと当時の様子に想いを馳せるとともに、150年の歴史を持つアンティークピアノが奏でるショパンの曲に耳を傾けるひと時。
ピアノ演奏は、山本貴志さんにお願いいたしました。
なお、この午餐と繋がるのは、2020年12月に最新刊が刊行された「ショパン全書簡」です。
この日本語への翻訳者の一人である関口時正さんより、書き下ろしのエッセイをお寄せいただきました。
(掲載許可済み)
外食するショパン
関口時正
ショパンはパリにいた間、自分がレストランで食べた料理の感想はおろか、何を食べたかということも手紙の中で書いてはいない。少なくともそういう手紙は残っていない。ただ、どんな料理屋に行ったかについては、わずかながら手がかりらしいものがある。パリに来てまだ日の浅い1831年11月18日、友人のクメルスキ宛てに書いた手紙には次のようなくだりがある(書簡89)――
人は誰もこの雑踏に埋没し、誰がどのように生きているのか関心を持つ者もいないので、その意味では気楽だ。冬でもぼろをまとって街頭を歩けもすれば 、最上流の人々の中に立ち交じることもできる――ある日の午餐に、黄金とガス〔灯〕とでもって煌々(こうこう)と照らされた、鏡張りのレストランで32スーの大御馳走にありついたかと思えば、次の日、三倍払っても小鳥の餌くらいしか出てこない朝食にあたることもある――
この「鏡張りのレストラン」は、パリ9区、テブ通りの北側にあった「カフェ・ド・パリ」を指すと思われる。カフェは現存しないが、当時は鏡張りの壁と赤いカーテンの内装、ムクドリやウズラを使った鳥料理で知られた。カフェの女性オーナーはイタリア人の血筋を引くマリア・エミリア・ファニャーニ、愛称「ミー・ミー」。彼女はイギリスの貴族シーモア=コンウェイと結婚してハートフォード侯爵夫人を名乗っていた。カフェの上の階では、ミー・ミーの息子のヘンリー卿が、イギリス人向けにボクシングやフェンシングのできるジムを経営していたという。カフェはレストランというよりむしろ常連客のためのクラブのような場所で、作家のアレクサンドル・デュマ(父)、詩人のアルフレッド・ド・ミュッセ、王立音楽アカデミー校長のルイ=デジレ・ヴェロンなどが通ったらしい。
同じ年のクリスマス、1831年12月25日、親友のティトゥス宛てに出した有名な手紙では、これから宴会に行くというこんな一節もある(書簡96)――
今から着がえて出かける、と言うより馬車に乗る。ロシェカナルにあるパリでも一番大きいレストランで、ラモリーノとランゲルマンのために催される今日の宴会には二、三百人集まるらしい。それに行く――数日前、クナチクがお人好しのビェルナツキと一緒に来て招待状を僕に届けてくれたのだ。
ラモリーノもランゲルマンも軍人、それも将軍である。ポーランド人ではなかったが、ポーランド人がロシア帝国に対して起こした反乱、いわゆる「十一月蜂起」で活躍した。この日は、蜂起が鎮圧されたポーランドの地を離れ、フランスに逃れてきた彼らを歓迎する祝賀の宴が開かれたのだった。ショパンが「ロシェカナルにある」と書いているのは、文字の見まちがえで、ただしくは「オ・ロシェ・ド・カンカル」というレストランのこと。当時パリでも最高級のレストランの一つで、パリ2区のモントルグイユ通りとマンダール通りの角にあった。特に芝居やオペラがはねた後に立ち寄る客に好評だった。現在も同名の店がモントルグイユ通り78番地にあるようだが別物で、ショパンが行った店は1846年に閉まっている。もともとは海産物の牡蠣を商う人物が1804年に開いた店なのでさぞかし美味しいオイスターが供されたのだろうと思う。店は1815年ごろに料理人ピエール・フレデリック・ボレルに売却されたが、ボレルも「牡蠣商」として登録されている公文書があるので、レストランではショパンのころにも牡蠣料理の伝統は生きていただろう。ちなみにボレルは自ら著した料理辞典を1825年に出版している。このレストランはバルザックの小説『幻滅』『骨董室』『娼婦盛衰記』などに登場する。
パリではなくトゥールの町で、1832年の夏の終わりごろ、ショパンは、彼がその後半生で最も親しくつきあった友人の一人であるフランコムと、同じくチェリストでパリ音楽院の先生ボディヨを、レストラン「ブール ・ドール軒」に招待している。この店は、トゥールの中心部、ロワイヤル通り(現在はナショナル通り)にあった古いホテルのレストランで、料理もワインも評判だった。第二次世界大戦でレストランは破壊された。
それから大分たって、1838年、ショパンはまたフランコムに宛ててこう書いている(書簡233)――
僕は今日、君を夕食の場所で待つ、フォワのカフェ(僕と同じ通りで、ムッシュー・カップの向かい側)で――六時に。それから君を自宅まで送る。君は着がえ、一緒にキナストンの家に行く。その間(かん)、六時から七時のあいだに、彼が君の妻を迎えに馬車を遣る。それでいいかな?
フォワのカフェは、ショセ=ダンタン通り2-4番地にあった、当時よく知られたレストラン。店の名は、ナポレオンのもとで活躍した有名な将軍・政治家、マクシミリアン・セバスティアン・フォワに敬意を表して付けられたもので、将軍は1825年にショセ=ダンタン通り62番地にあった自宅で他界していた。ショセ=ダンタン通り2番地の建物には、1848年からジャコモ・ロッシーニが住んでいた。なお、パレ=ロワイヤルの中にあった有名店「カフェ・ド・フォワ」はまた別の店である。
結局のところ、こうして料理屋の名前を並べても、ショパン自身の手紙からは、彼が何を食べ、どんな感想を持ったのかはわからない。彼の友人や弟子の証言でも丹念に読めば、何か出てくるかもしれないが、残念ながら今の段階では私はそれをしていない。
おまけとしてひとつだけ、料理でもレストランでもないのだが、引用しておきたいショパンの言葉がある(書簡258)――
別のものと取り違えられ、地面から引き抜かれて食べられたが最後、食あたりをおこすシャンピニョン 、僕はそんな毒キノコに似ているが、それは僕の罪じゃない――一度として僕は人の役に立ったことがないのはわかっている――しかし僕は、自分自身にとってもたいして役に立ちはしなかった。
これはマジョルカ島の旅をすでに終え、マルセイユから友人のフォンタナに宛てて書いた手紙にある言葉である。自分は、あるいは自分の音楽は、一見するといかにもおいしそうに見えるが、あいにく人はそれで食中毒にかかる。偽りの看板を掲げて人をだましているわけではなく、あえておいしそうな曲名を付けるわけでもない。自分が、あるいは自分の音楽が、「人の役に立つ」ような性質のものではないということを、ショパンにしてははっきりと表現している。
原文でszampinionという語を使っているが、これはフランス語(champignon)の音を写したもので、ポーランド語ではない。ショパンお得意の造語である。ポーランド語にはピェチャルカ(pieczarka)とかグジプ(grzyb)いうキノコを表すれっきとした言葉があるのに、わざと異質な、珍しい感じを与える言葉を造り、しかも下線を引いて強調しているのである。この手紙では、作品40-2のポロネーズをフォンタナに献呈しながら、これが君に対する僕の返事だというようなことも言っているが、フォンタナの質問がどのようなものだったかはわかっていない。
自分の音楽は、一般の人々には理解しがたい、消化しがたいものが多く、生活や社交の用にも不向きなものだということの自覚がここにはある。だからと言って、違う音楽を、おいしく、役立つ音楽を作るつもりはない、あるいは作れない――ショパンの孤独の基礎のようなものがここには表現されているというのが私の考えである。
(書簡番号は岩波書店刊『ショパン全書簡 パリ時代』上下巻のもの)
また、当日の様子を映像として記録いたしましたので、併せてお楽しみくださいませ。
https://youtu.be/4ExVnojP0XQ
撮影:Maciej Komorowski
ご協力:レストラン パッション、 一般財団法人 欧州日本藝術財団、 駐日ポーランド共和国大使館